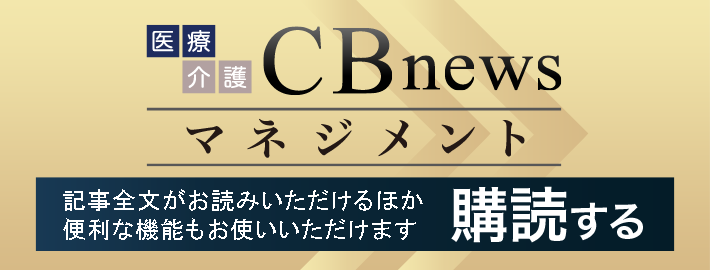【北海道介護福祉道場 あかい花代表 菊地雅洋】
介護人材不足と言われて久しい。2000年度の介護保険制度の施行後、介護職員数は毎年増加していたが、要介護者らの増加数に介護職員の増加数が追い付かず、介護人材不足が深刻化してきた。
24年12月25日に厚生労働省が公表した集計結果によると、介護事業者に所属する介護職員数が23年10月1日現在で約212.6万人と前年と比べて約2.9万人減少していることが明らかになった。要支援者と要介護者が前年比8万人増えている同じ年に、介護保険制度の創設以後、介護職員数が前年比で初めて減少に転じたことに衝撃を受けている介護関係者は少なくないだろう。
この結果によって今後の介護事業者にとって人材確保がますます困難になることが予測されるからだ。事業者は介護DXなどを推進し、各種業務の省力化を図りながら介護労働の生産性を向上させる取り組みが必要となる。全従業員が同じ方向を向いて一丸となって改革に取り組む必要性が増す。ところが、その際のバリアとなっているのが「職員同士の世代間ギャップ(感覚の違い)」であると嘆く関係者が少なくなく、価値観や考え方のギャップをどう埋めるか悩む管理職も少なからず存在する。
だが、介護事業以外の仕事ではこのような悩みを耳にすることはあまりない。そもそも、異なる世代が混在するのが職場だ。世代を超えてつながり合って、ベテランが若い世代にノウハウを伝えてつなげていかないと組織は存続できない。そのためベテランから新人まで、さまざまな世代の人びとを集めて組織の血肉にしていく必要がある。
生きてきた時代が異なる人が集まれば、それぞれの考え方に違いが生じるのは当たり前だ。しかし、そうした考え方の違いが仕事のパフォーマンスに影響を与えては組織が成り立たない。世代間ギャップを超えて、
(残り1493字 / 全2254字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】